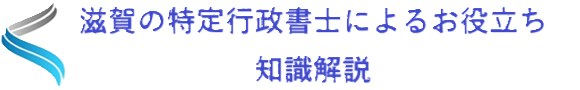昨今、人手不足はどの業界でも深刻な問題となっています。外国人の雇用を考えておられる事業者も多いと思いますが、在留資格(「ビザ」と呼ばれる場合もありますが厳密には別物です。)の知識を持っておかないと、知らずに法律違反を犯しかねません。
そこで、今回は外国人の雇用を考えておられる方向けに、在留資格についてお話ししていこうと思います。
外国人雇用における在留資格の重要性
在留資格とは?その基本を解説
在留資格とは、日本に在留する外国人がどのような活動を行うことができるかを法的に定めた制度です。
外国人は、在留資格に基づいた活動のみが許可され、それ以外の活動を行う場合には、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。
日本には29種類以上の在留資格があり、それぞれに許可される活動内容、在留期間、取得要件が定められています。
在留資格の種類と特徴
在留資格は大きく分けて以下の3つのカテゴリに分類されます:
- 就労系の在留資格(例:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、技能実習など)
該当する在留資格の活動範囲内での就労が可能で、範囲外の就労を行うには、資格外活動許可を取得する必要があります。 - 非就労系の在留資格(例:文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)
収入を伴う事業を行うことや就労して報酬を受けることはできません。資格外活動許可を受ければ、アルバイト等は可能です。 - 身分・地位に基づく在留資格(例:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
就労等の活動に制限がなく、日本人と同じように仕事をすることができます。
各資格には、適用される活動範囲と制限があり、目的に合った資格の取得が必要です。
法務省の外局の出入国在留管理庁の出先機関である各地の出入国在留管理局が審査し、認められれば取得できるものです。
なお、在留資格は、1人の外国人の方に対し、必ず1つしか認められません。
在留資格の変更と更新のプロセス
在留中に活動内容や滞在目的が変わる場合、出入国在留管理局に対して「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
また、在留期間が満了する前に継続して滞在するには「在留期間更新許可申請」が必要です。
いずれも、理由書、在職証明書、収入証明、税証明など複数の書類を揃え、正確に提出することが求められます。
就労に必要な在留資格の取得方法
就労系の在留資格(就労ビザ)とは?必要書類と申請手続き
就労系の在留資格(就労ビザ)は、日本国内で合法的に労働するために必要な資格です。主な種類には「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」などがあります。
申請時には、
- 雇用契約書
- 大学等の卒業証明書
- 職務経歴書
- 勤務先の登記事項証明書、決算書
などを提出し、活動の妥当性と経済的安定性を証明する必要があります。
特定技能ビザの概要と申請条件
「特定技能」は、深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格で、特定技能1号では特定産業16分野での就労が可能です。
特定技能1号
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲料食品製造業、外食業、林業、木材産業(特定産業16分野)
在留期間:1年未満ごとの更新が必要で最長5年間の在留が可能
技能水準:産業分野ごとに実施する試験等合格が必要(技能実習2号修了者は免除)
日本語能力水準:試験(N4等)合格が必要(技能実習2号修了者は免除)
家族の滞同:不可
その他:受け入れ機関又は登録支援機関による支援を必要とする。
特定技能2号
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲料食品製造業、外食業(特定産業11分野)
在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限がない)
技能水準:産業分野ごとに実施する試験等合格が必要(技能実習2号修了者は免除)
日本語能力水準:試験なし(漁業、外食業はN3以上必要)
家族の滞同:要件を満たせば配偶者・子供は可能
外国人のための就労可能な資格の違い
就労系の在留資格には、活動内容や転職の可否、在留期間に大きな違いがあります。
- 技術・人文知識・国際業務:大卒レベルの知識を要する職務(例:通訳、エンジニア)
- 技能:熟練した職人技術が必要な職務(例:料理人、自動車整備)
- 技能実習:技術移転を目的とした制度。基本的に転職不可。
- 特定活動:内定を得た留学生の就職準備活動など、個別に認定される活動
など
在留資格更新の重要なポイント
在留資格更新のための手続き
在留資格の更新申請は、原則として在留期限の3か月前から可能です。必要書類は資格によって異なりますが、主に以下のものが必要です。
- 在職証明書
- 所得証明書、住民税課税証明書
- 直近の給与明細
- 雇用主からの更新理由書
期限を過ぎての申請は原則認められず、不法残留となるリスクがあります。
更新申請が不許可となる事例
更新申請が不許可となる主な理由には次のようなものがあります:
- 活動実態が在留資格に合致していない
- 税金・社会保険料の未納
- 雇用契約の終了後に転職せずに滞在
- 虚偽書類の提出
適切な準備と、行政書士等の専門家への相談が重要です。
在留カードの更新について知っておくべきこと
在留カードの有効期限は在留期間に応じて設定されています。
更新には写真、身分証明、理由書などが必要で、紛失時には速やかに届出・再交付手続きが必要です。
また、永住者の場合もカード更新が必要で、忘れると罰則があります。
日本での外国人雇用に関する法律と制度
出入国管理法の理解とその適用
出入国在留管理庁が運用する「出入国管理及び難民認定法(入管法)」は、外国人の入国・滞在・退去に関する包括的な法律です。
雇用主は、外国人の在留資格確認義務を負っており、資格外の活動をさせた場合には罰則を受けることもあります。
雇用契約と在留資格の関連性
雇用契約の職務内容が在留資格に合致していない場合、違法就労とみなされる恐れがあります。
採用時には在留カードを確認し、「就労制限の有無」欄に注意する必要があります。
また、職務変更や転職時には在留資格の変更申請が必要になるケースもあります。
登録支援機関の役割と活用法
特定技能1号の在留資格で外国人労働者を雇い入れる事業者は、「特定技能外国人支援計画」を作成し、作成した計画に基づいて雇い入れた外国人の日本での生活の支援を行わなければなりません。
この支援を、事業者で自らで行うこともできますが、第三者に委託することもできます。
特定技能1号の外国人に対しては、登録支援機関が特定技能外国人の生活支援(住居探し、日本語教育、生活相談)などを行い、職場定着をサポートしています。
登録支援機関に依頼することで、企業側の負担も軽減され、スムーズな受け入れが実現します。
登録支援機関は各地にあり、出入国在留管理庁のホームページなどで簡単に調べることができます。
在留資格の留意点と注意事項
資格外活動とその制限について
留学生や家族滞在者など就労を目的としない在留資格では、原則として働くことはできません。
ただし、事前に出入国在留管理局で「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能となります。
無許可での就労は、在留資格の取消や退去強制の対象となります。
在留資格取得時の注意点
申請時の提出書類は、虚偽や矛盾がないように整える必要があります。職務内容、雇用条件、本人の経歴との整合性が取れているかが審査の大きなポイントとなります。
また、通訳や事務などの職種であっても、学歴や職歴が問われるため、準備には時間が必要です。
日本人との違いと求められるスキル
外国人労働者には、日本語能力や異文化コミュニケーション能力、在留資格に沿った専門性が強く求められます。
雇用主側も、文化的な違いを理解した上での受け入れ体制構築が重要です。
永住者としての在留資格の取得
永住資格の要件と申請プロセス
永住許可を得るには、原則10年以上(うち5年以上は就労資格等で在留)、安定した収入、納税義務の履行、素行が善良であることなどが求められます。
申請には詳細な収入証明、納税証明、理由書、保証人が必要となり、審査期間は半年~1年以上かかることもあります。
永住ビザのメリットとデメリット
メリット
- 在留期間の制限がなくなる。
- 職種・転職の自由度が増す。
- 住宅ローンなどの取得がしやすくなる
デメリット
- 申請に必要な書類が多く、審査が厳格
- 一度取り消されると再取得が困難
成功事例と失敗事例の考察
成功事例では、納税記録や勤続年数、扶養家族の安定性などが重視され、事前準備が整っていたことが多いです。
一方、失敗例では、収入不足、頻繁な転職、過去の交通違反などが原因で不許可になる傾向があります。
今後の在留資格制度の展望
国際情勢と在留資格に与える影響
新型コロナウイルスや国際紛争、地政学的リスクの影響で入国規制が厳しくなった事例もあり、世界的な動向は日本の入管政策にも直結します。
災害やパンデミック時の特例措置などにも注視する必要があります。
日本の人材不足と外国人雇用の関係
人口減少と少子高齢化により、特に建設、介護、農業、宿泊・外食業などの分野で外国人労働力への依存が強まっています。
外国人材の活用は、国の成長戦略の一環として不可欠な存在となっています。
新たに設けられる在留資格の動向
今後、デジタル・グリーン分野などの新産業への対応として、新たな在留資格が検討される可能性があります。
政府の制度設計の動向に注目し、事業者側も情報を常にアップデートしておくことが重要です。
まとめ:外国人雇用と在留資格を理解しよう
必要なステップを整理する
- 在留資格の確認・選定
- 必要書類の収集
- 出入国在留管理局への申請
- 許可後の入国・在留カード取得
- 雇用契約と就労開始
- 定期的な更新と適正管理
各種サポート機関の活用法
- 行政書士:申請書類の作成・代理提出
- 登録支援機関:生活・就労サポート
- 地方自治体や国際交流協会:日本語教室、相談窓口などの支援
- 外国人雇用サービスセンター:職業紹介やマッチング支援
今後の展望と雇用機会の変化
外国人雇用は今後も拡大傾向にあり、企業にとっても多様な人材を活用する好機です。
在留資格制度の理解と適正な運用を通じて、持続可能な人材確保と社会的共生を目指しましょう。